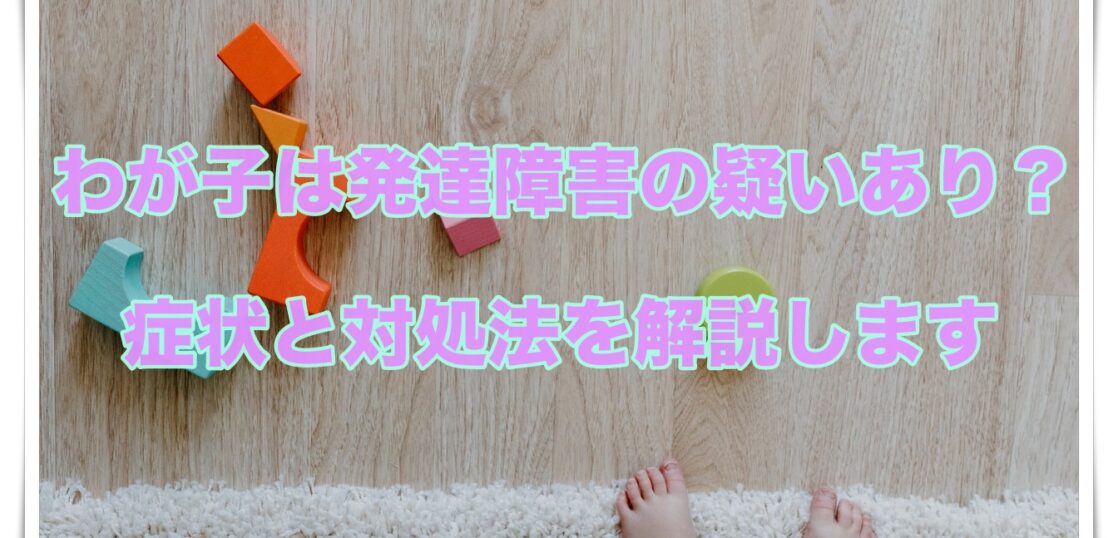皆さんこんにちは!本日も知って役立つ情報をみなさんと共有していきます!今回のキーワードは「発達障害の疑い」についてです。
今回は、発達障害を疑うべき症状と対処法についてお伝えします。
お子さんの発達障害を見落とさないためにも、可能性のある症状や対処法についてくわしくみていきましょう。
目次
発達障害を疑うべき症状とは

発達障害にはさまざまな症状があり、人によって程度も異なります。
発達障害を疑うべき症状について、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)、LD(学習障害)のそれぞれの種類ごとにみていきましょう。
・視線が合いづらい
・無表情
・名前の呼びかけに反応しない
・人見知りせず親の後追いもしない
・ひとりごとが多い
・オウム返しをする
・触られるのを極端に嫌がる
・ひとり遊びを好む
・好き嫌いへのこだわりが強い
・ほしいものを親の手を使ってとろうとする
参照:こころの健康情報局 「すまいるナビゲーター」
・目の前のことに集中できない
・ものをなくしやすい
・手順どおり取り組めない
・じっとしていられない
・待てない
・人の邪魔をしてしまう
・おとなしく遊べない
参照:e-ヘルスネット
・単語や文の途中で区切って読む
・指でなぞりながら読む
・読みながら行を間違える
・読めない文字をとばす
・文末などを適当に読む
・音読みか訓読みのどちらかしかできない
・助詞や促音などを書き間違える
・形の似た文字を書き間違える
・数字の大小が理解できない
・数が数えられない
・いつまでも指を使って計算する
・繰り上がりや繰り下がりが理解できない
・九九が覚えられない
参照:e-ヘルスネット
発達障害の特徴について、年齢別にくわしく解説した動画がありますので、参考にご覧ください。
このように、発達障害の特徴は誰にでも少しは当てはまるような特徴であるため、症状が軽い場合は発達障害であることになかなか気づけない場合もあります。
大切なことは、お子さんが日常を過ごす上で何か困っていることはないか、支援が必要なことはあるか、お子さんから出る小さなサインを見逃さないことです。
では、その小さなサインに気づいた場合、どのような行動をすればよいのでしょうか。
発達障害の疑いに気づいた場合の対処法について、くわしくみていきましょう。
発達障害の疑いに気づいた場合の対処法

発達障害の疑いに気づいた場合は、ご家族だけで抱え込まずに専門機関に相談することが大切です。
しかし、注意が必要なのが誤診についてです。
近年、発達障害の早期発見が重要視される一方、診断を急ぎすぎて誤診をしてしまうケースが増加しています。
次のツイートをご覧ください。
このように、医療機関などで発達障害の疑いがあるといわれても、発達障害の専門機関で実際に診断されるのはその中の一部の方です。
発達障害の診断はとても難しく、チェックリストなどの簡単な調査だけでは不十分です。
家庭や保育園などでの行動やこれまでの生育歴などの情報を集め、時間をかけてじっくり判断する必要があります。
早期発見にとらわれ過ぎて簡単な調査結果だけを鵜呑みにしてしまうと、後々誤診であることに気づく場合もあります。
もしもお子さんの発達障害の疑いに気づいた場合は、信頼できる専門性の高い機関で時間をかけて相談しましょう。
続いて、発達障害について相談できる専門機関について紹介します。
発達障害について相談できる専門機関

発達障害について相談できる専門機関はさまざまな場所にあります。
それぞれに特徴がありますので、ひとつずつ紹介します。
地方自治体の発達相談窓口
各自治体には、お子さんの発達について気軽に相談できる窓口があります。
名称は自治体により異なりますが、障害関連の課や子ども・健康関連の課に併設されていることが多く、保健師や看護師、家庭児童相談員などの専門職が常駐している場合もあります。
発達障害の診断はできませんが、状況に応じてほかの専門機関へ紹介してくれる場合もあるので、お子さんに気になることがある場合には気軽に相談してみましょう。
発達障害者支援センター
発達障害者支援センターは、当事者とご家族をとりまく医療・福祉・教育などさまざまな専門機関と連携し、相談や支援を行っています。
全国各地に設置されていますが運営者はさまざまなので、お住まいの近くの発達障害者支援センターについてぜひ調べてみてください。(発達障害者支援センター一覧)
医療機関
発達障害かどうかを確かめるためには、医師の診断が必要です。
しかし、発達障害の診断には専門性が必要なため、すべての医師が診断できるわけではありません。
発達障害を診断することができる小児神経専門医についての一覧がありますので、医療機関で診断を受ける際には参考にご覧ください。
子育て支援センター
子育て支援センターは子育て支援の拠点として全国各地に設置されています。
保育園などに併設されることもあり、保育士や保健師、心理職などの専門職が相談支援を行っています。
発達障害をはじめとして子育てに関するあらゆることを気軽に相談することができます。
親子の交流の場などもありますので、子育てに息詰まった場合や、負担を感じている場合にも、気軽に足を運んでみましょう。
参考:東大阪市 子育て応援なび
児童相談所
児童相談所はお子さんやご家族の福祉のために、高度な専門知識を用いてさまざまな援助活動を行っています。
児童福祉司、相談員、児童心理司、児童指導員、保育士、精神科医、小児科医、保健師、理学療法士、臨床検査技師などあらゆる分野のプロフェッショナルで構成されているため、子育てについて総合的に相談することが可能です。
発達障害については、医師と連携しながら調査・診断・判定などを行っています。
発達障害の疑いのあるお子さんを含め、ご家族全体にとってもっとも効果的な方法で専門家たちが支援してくれるので、子育てに不安を感じている場合はぜひ相談してみてください。
児童デイサービス
児童デイサービスでは、放課後や休日などに個々のお子さんの状況に合わせてさまざまな支援を行っています。
こちらの記事を掲載している大阪府のライズ児童デイサービスでは、お子さんの精神的・身体的機能を最大限に伸ばすことを目指して支援をしています。
見学を受けつけている施設もありますので、ぜひ一度のぞいてみてください。
参考:ライズ児童デイサービス
このように、発達障害の相談先はさまざまです。
どこに相談すればよいか迷ってしまう場合は、まずはお住まいの自治体の発達相談窓口に相談しましょう。
お子さんやご家族を含めて総合的に相談ができ、必要に応じてほかの専門機関へ紹介してもらうことが可能です。
ご家族で抱えてしまうことはお子さんのためにもよくないので、ほんの小さなことでも気になることがある場合には、気軽に相談してみましょう。
そして誤診を防ぐためにも、じっくりと時間をかけて結果を焦らないことを意識しましょう。
では、実際に発達障害の診断を受けた方はどのような経緯で診断を受けているのでしょうか。
実際の体験談を紹介します。
発達障害の診断を受けるまでの実際の体験談

発達障害の診断は、時間をかけてじっくり判断することが重要です。
実際に発達障害であると診断されるまでの経緯を紹介した動画がありますので、紹介します。
このように、発達障害であると診断されるまでには、ご本人だけでなくご家族にも相当な葛藤があることがわかります。
発達障害の症状は定型発達のお子さんにも共通してみられることが多いため、親御さんは「わが子は発達障害ではない」と信じたくなるものです。
大切なのは、発達障害であると診断されることではなく、お子さんにとって必要な支援を適切に行うことです。
必要な支援を適切に行うためには、お子さんが困っている背景について知る必要があるため、そのために行われるのが発達障害の診断です。
診断の結果にまどわされず、「わが子にとって必要な支援とは何か」を常に意識しましょう。
まとめ
今回は、発達障害を疑うべき症状と対処法についてお伝えしました。
・お子さんから出る小さなサインを見逃さないこと
・じっくりと時間をかけて専門性の高い機関で診断を受けること
・お子さんにとって本当に必要な支援を適切に行うこと
以上の点を意識し、少しでも気になる点がある場合には、気軽に専門機関に相談しましょう。
そして、お子さんやご家族にとっての困りごとをひとつでも軽減させていきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。