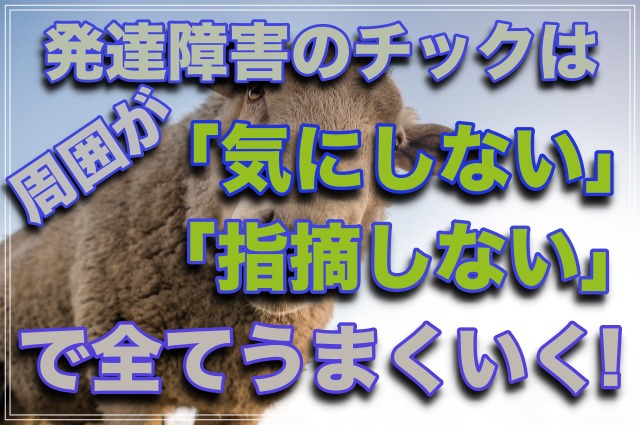皆さんこんにちは!本日も知って役立つ情報をみなさんと共有していきます!今回のキーワードは「発達障害とチック」についてです。
今回は、発達障害のひとつであるチックについてお伝えします。
「チックは指摘しない方が良い」と言われている理由について、くわしくみていきましょう!
目次
発達障害のチックは指摘しない方が良い理由

発達障害のひとつである「チック」は、次のような状態を言います。
意思とは関係なく身体の一部が動いたり声を発したりしてしまうこと
チックは指摘しない方が良いといわれている理由は次のとおりです。
・成長にともない、自然と良くなることがほとんどであるため
・本人の意思で症状をコントロールできるわけではないため
・本人が気にすると意識がチックに向いてしまい、悪化する恐れがあるため
・良いところに注目して自信をつけると、症状が良くなる場合があるため
このように、チックの症状を良くするためには、「本人も周りの人も症状を気にしないことが一番」であるといえます。
ほとんどの子は成長に伴い緩和されていく
チックはひどい場合には薬などを使って治療する必要がありますが、ほとんどの場合は成長にともない自然と良くなるため、無理に治そうとする必要はありません。
チックを指摘すると本人の意識がチックに向いてしまい症状が悪化する可能性もありますので、周りの人はチックの症状に注目しないようにしましょう。
また、良いところを褒めてもらうことで自信がつくと症状が良くなる場合もありますので、良いところに注目し自信を増やすための支えになりましょう。
お子さんがチックと診断された場合の対処法が知りたい方はこちらの動画をご覧ください。
では、「チックにはどのような種類がある」のでしょうか。
症状を指摘しないためにも、チックについての理解を深めていきましょう。
チックの種類

チックには大きく分けると、次の2つ。
- 運動チック
- 音声チック
いくつかの運動チックと、1つ以上の音声チックが『1年以上』続く場合、次のように呼ばれます。
トゥレット症候群
それぞれの症状について、くわしくみていきましょう。
運動チック
運動チックは、本人の意思とは関係なく身体の一部がくりかえし動いてしまうことをいいます。
具体的な症状は次のとおりです。
・まばたきをたくさんする
・鼻をひくひく動かす
・口をまげる
・口をあける
・舌を出す
・首を動かす
・腕を動かす
・足を動かす
・お腹を動かす
音声チック
音声チックは、本人の意思とは関係なく声をくりかえし発してしまうことを言います。
具体的な症状は次のとおりです。
・風邪ではないせきやせきばらいをする
・鼻をならす
・舌をならす
・叫ぶ
・「あ」や「お」など声を出す
・言葉を連発する
・「うるさい」など汚い言葉をいう
トゥレット症候群
トゥレット症候群は神経発達症のひとつであり、複数の運動チックとひとつ以上の音声チックが『1年以上』続くことをいいます。
・多くは子供の頃に発症する
・チックの動作回数は増減する
・他の発達障害と併発することも
併発する場合も、症状を含めて理解し、社会に適応できるように周りが支援することを目標としていきます。
そもそも、チック症状は『なぜ』起こるのでしょうか。チック症状の起こる『原因』をくわしくみていきましょう!
チックの症状がおこる原因

チック症状がおこる原因はハッキリとは解明されていません。
しかし、次のような原因が考えられています。
【遺伝要因】
脳内回路や神経伝達物質の異常
【環境要因】
テレビの見過ぎによる目の疲れ、結膜炎による目のかゆみ、風邪により咳がくせになった、など
【心身要因】
不安、緊張、疲労、興奮、ストレス
このように、「生まれつきの要因」と、「生活環境による要因」が考えられています。
脳内の異常については自分の力で改善することは難しいですが、環境要因や心身要因については生活を見直すことでチックの発症を防ぐことができるかもしれません。
環境や心身の要因はチックだけでなくさまざまな疾患につながる可能性もありますので、日頃からできるだけストレスを抱えないよう配慮しましょう。
では、実際にチックの症状を抱えている方は、どのような体験をされているのでしょうか。
実際の声を聞いてみましょう!
チックやトゥレット症候群を抱えている方の体験談

チックを発症している方は、生活の中でさまざまな困難を体験しています。
しかし、その中でうまくつきあうための方法を模索している方もたくさんいます。
実際にチックの症状とどのようにつきあっているのか、体験談をみてみましょう!
トゥレット症候群は 辛く苦しく 孤独になります。
だから その気持ちをわかってくれる友達。友達。わかってくれる、普通に自然に 寄り添ってくれる友達
家族がいてくれたら どんなに心強いかとおもいます
友達。友達。友達。
友達に出会えたらいいな
引用元:ツイッター
こちらは、トゥレット症候群(チックが1年以上続いている状態)は苦しくて孤独なため、その気持ちを理解してよりそってくれる友達に出会いたいという声です。
「周りの理解」が全てを解決すする
昨日久々に焼肉屋さんへ。
息子が 「ここだったらオレでも働けるかも!こんなにザワザワしてるなら大丈夫そう!」 と言っていた。
普段ボーッとしている中2男子だけど 先々のことを考えてる?
音声チックがあると 生きづらいことが多いけど 上手く共存していく道を 息子は模索しているのかな。
引用元:ツイッター
こちらはザワザワしている環境なら音声チックがあっても働けるかもしれないと将来を模索している方の声です。
また、有名人の方にもチックやトゥレット症候群と向き合っている方がいますので、紹介します。
このように、チックやトゥレット症候群とうまくつきあうためのキーワードは「周りの理解」です。
周りの人が理解をすることで、チックの症状をガマンする必要がなくなり、安心して人との時間を過ごすことができます。
周りの理解がお子さまには必要
かなり勇気のいることかもしれませんが、周りに知ってもらうと、適切な接し方も理解してもらえます。
だからこそチックやトゥレット症候群であることを周知したり、この症状への知識を広めていくことが大切であるといえます。
まとめ
今回は、発達障害のひとつであるチックについてお伝えしました。
- 症状が出ても指摘しない方が良い
- 環境や心身を整えることが先
- 周りの『理解』がとても大切
ご本人と周りの人とで連携して、チックとうまくつきあっていきましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。