皆さんこんにちは!本日も知って役立つ情報をみなさんと共有していきます!今回のキーワードは「子育て忍耐」についてです。
日常の子育てに関する様々なシーンにおいて、「なぜ言うことを聞いてくれないのか」、「どうしてこのような行動をとるのだろう」等、子どもの行動に対してフラストレーションを感じる場面が多々あるのではないでしょうか。
この記事では、親としての忍耐力を養う術を紹介していきます。
記事を読んだ後は、子どもとちょうどよい距離感を保ちながら、感情を高ぶらせることなく関われるはずです。
目次
親の「忍耐力」が子どもに与えるメリット
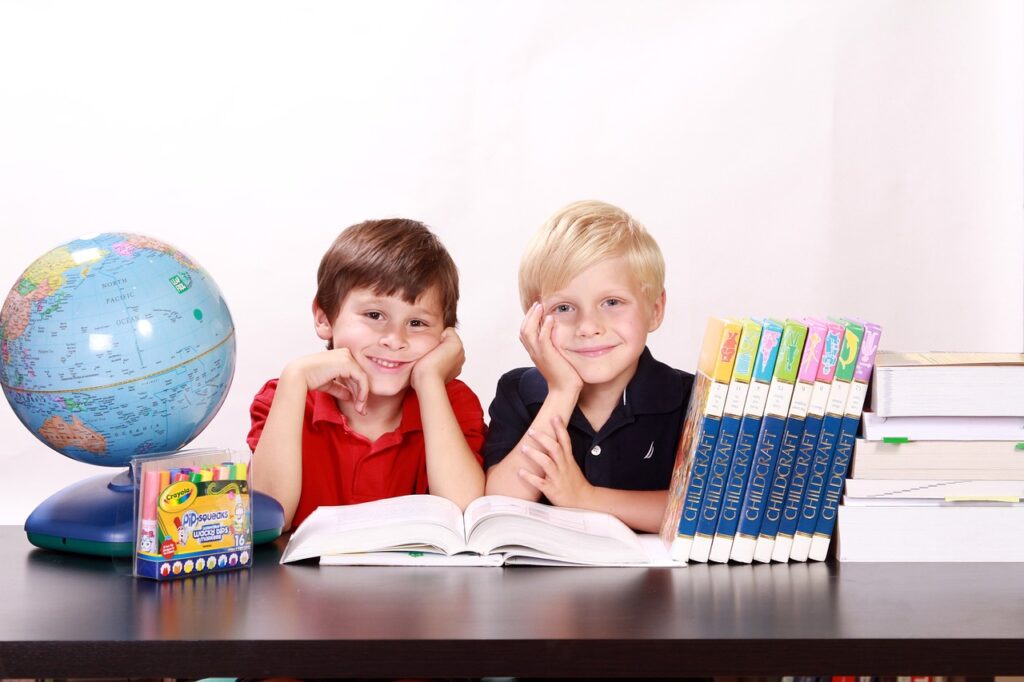
独創性が養われる
例えば、勢いよく木に登る我が子を見て、登ったばかりなのに「危ない!」と言って、登ること自体を静止するのではなく、親の胸の高さあたりまでは補助をしながらまずは登らせてみる、といった体験を積ませることも大切です。
親として心配であるが故に、すぐさま手を差し伸べてしまいがちな場面も多いかと思います。
安全性が確保された状態であれば、子どもの意欲のままに遊ばせてみることで、子どもは様々な遊びを考え、周囲を巻き込みながら遊びます。
その体験の積み重ねが、豊かな独創性を育む一助となるはずです。
自己肯定感の構築
自分の行動に対し、親が肯定的に関わることで、子どもは「自分の考えは認めてもらっている」と感じるようになります。
命の危険や他者に危害を加えるおそれのある行動以外は、子どもの遊びや行動を尊重してあげることが大切です。
子どもが、悪ふざけやいたずらをしてしまった場合でも、一方的に叱るのではなく、「なぜそうなったのか?」という視点で、子どもと一緒に原因を考えてくれる親の存在は、とても大きなものとなるでしょう。
責任感の構築
親から「そうしてはいけない」「これはこうしなさい」など、一つひとつの行動に対して指示されて動くのではなく、自分の意思に基づいて行動する力を身に着けていくことは、責任感の構築に繋がっていきます。
子どもが自分で考えて行ったことについて、失敗すれば一緒に反省して、成功体験に繋がるものであれば大いに褒めてあげることが大切です。
行動の結果が「自分の意思に基づくもの」であるという認識を高めていくことは、子どもの成長に繋がる重要な要素となります。
親が、「忍耐力」をもって子どもと接するメリットを理論的に理解できても、「実際の子育て現場では毎日が修羅場なんです!(泣)」と悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
次の章では、親が子どもに対して「イライラしてしまう」「つい感情的になってしまう」ことが多い場面をあげてみたいと思います。
親が忍耐を強いられる子どもの行動

着替え等
3歳くらいになると自我が芽生え、「自分で服を着たい!」、「自分で靴を履きたい!」という意欲が行動に現れてきます。
しかし、なかなかうまく着られず時間がかかってしまうこともあり、親が過剰に手伝ってしまうことも多いのではないでしょうか。
自分でやってみたい子どもの行動を中断させることになるので、子どもと衝突してしまうパターンも少なくありません。
食事の問題(食べない・離席・遊ぶ)
栄養バランスを考え、真心込めて作ったごはん。
家族みんなで、いただきます!のあいさつ後間もなく、お皿をひっくり返したり食べ物で遊ぶ、席を立って走り回る等といった行動をとる我が子…。
3歳頃までは、集中力が続かず遊びに意識が移行しやすく、場面の切り替えについて辛抱強く教えていかなければなりません。
買い物中に駄々をこねる
「お菓子は買わないよ。」と、買い物前に約束したはずなのに、スーパーに着いたとたん「お菓子買ってー!」と、泣き叫ぶケース、よくありますよね…。
公の場で、駄々をこねて泣き叫ばれたら、周囲の目が気になったり、どう対応していいのかわからなくなり、焦ってしまうことが多いと思います。
思わず、「うるさい!周りの人に迷惑でしょ!」等と、感情的に子どもに向き合ってしまうことも多いのではないでしょうか。
その他にも、
・夜泣き対応
・片づけをしない
・親の声掛けを無視する、など。
親の「忍耐力」が試される場面は、日常の中に数多くあるのです。
日々子育てに奮闘し頑張っているあなたが、子どもとの関わりで疲弊してしまわないためにも、次の章で「忍耐力」を養うためのステップについて学んでいきましょう
「忍耐力」を養うための4ステップ
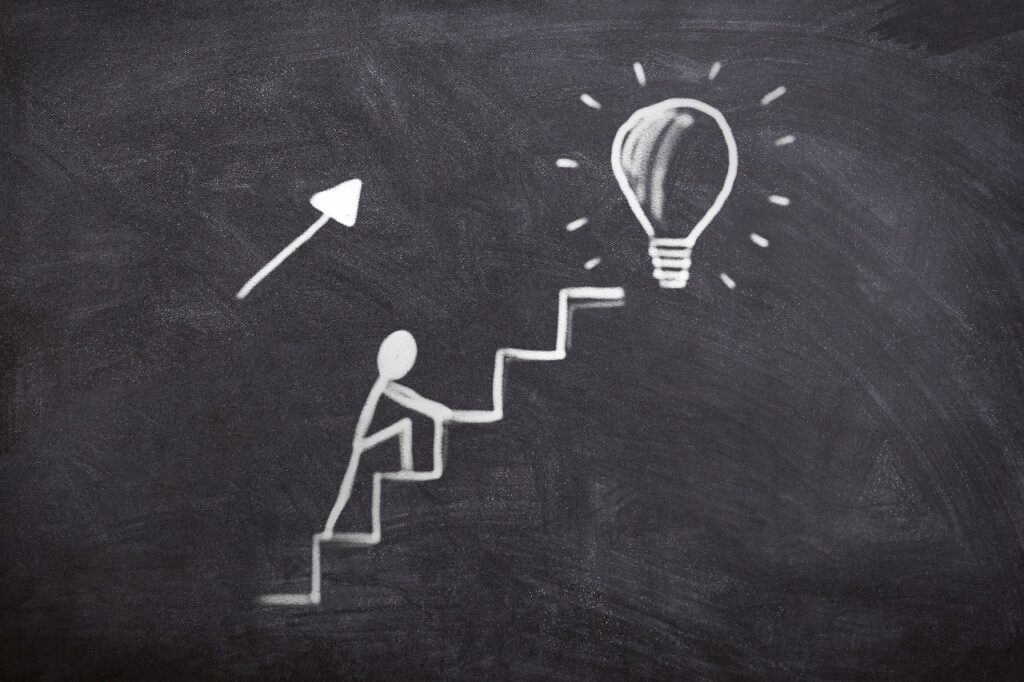
感情が高ぶる自分を責めないこと
我が子に対し、「正しいこと」や「正しいやり方」を教えていきたいという気持ちが強いことから、「親の要望や想定通りに行動しない」と、「感情的に接してしまう」、というループに陥ることも少なくありません。
しかし、これらの事柄に対してイライラすることは人の感情として当たり前のこと。
「またイライラしちゃった…」等と、自分を責めることはやめましょう。
子どもの安全を確保したうえで行動を「許容」すること
子どもの行動一つひとつに敏感に反応するのではなく、「このレベルであれば許せる」や「ここまでなら子どもの意見を尊重できる」といったような、許容範囲を明確にしておくことが大切です。
「命の危険・ケガを負う危険がないこと」「他者に危害を加えるおそれがないこと」といった、この2点に当てはまっているのであれば、子どもの遊びや行動を否定せず、大いに尊重してあげましょう。
親としての「理念」を伝えていく
ここでいう「理念」とは、ママやパパの基本スタイルのようなもので、「親が子に伝えたい価値観」を伝えていくことが大切です。
「ママは、挨拶をとても大切にしている。あなたにも挨拶の大切さを知ってほしい」など、親がもっとも大切にしている考え方や行動を、普段の生活の中で伝えていくことが大切です。
例えば、上記のように「挨拶をしっかりできる子になってほしい」という思いを貫くために、親が率先して挨拶する姿勢を見せることが重要です。
それに加えて、子どもが挨拶する場面でしっかり挨拶ができなかった場合は、「挨拶はしっかりしなければいけない」と、毅然とした態度で伝えていくことが大切です。
親として譲れない場面でしっかりと子どもに思いを伝える場面と、許容できる場面を明確に分けておく。
そのバランスが、子どもにとってもインパクトが大きく印象に残る伝え方となるのです。
親の「理念」は詰め込みすぎない。多くて3つ程度
あれもこれも身に着けてほしい、というような事になると完璧主義的な思考に陥ってしまいます。
ママ、パパの間で話し合って、子どもの教育において重要なキーワードをあげながら、ポイントを絞って考えるとよいでしょう。
あれもこれもと、「できるようになってほしい」という思いで指摘や叱ってばかりいると、子どもにとっても単純に「うるさい」存在で終わってしまう可能性があります。
親からの「こうなってほしい」という思いは、子どもにとってはプレッシャーに感じることでもありますので、子どもの性格等も考慮しながら伝えていくことが大切です。
まとめ
それでは、上記の内容を整理していきましょう。
・独創性が養われる
・自己肯定感の定着
・責任感の構築
・感情が高ぶる自分を責めないこと
・子どもの安全を確保したうえで行動を「許容」すること
・親としての「理念」を伝えていく
・親の「理念」は詰め込みすぎない。多くて3つ程度
忍耐力をつけていくためには、何度も反復して練習することが大事です。
ときにはカッとなる場面もあるかと思いますが、この記事で学んだことを振り返りながら、子どもと一緒に親も成長していきましょう。

